「先」を「おんな城主 直虎」で解説してみた
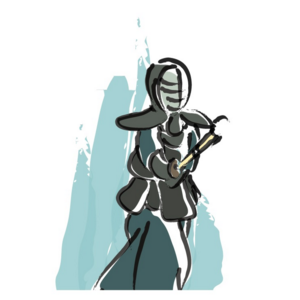
今年の大河ドラマもかなり面白いですね。
その大河ドラマ「おんな城主 直虎」で剣道ネタになりそうな話がありましたので解説してみます。
ドラマの主人公は井伊直虎。その養子である万千代が徳川家の草履番となった話がそれです。
ちなみに万千代は後の彦根藩初代藩主となる井伊直政です。
時は長篠の合戦が始まろうとする頃ですので、徳川家もかなりの大所帯となり、その草履番も大忙しです。
とくに下城する際には家臣が一斉に玄関へと向かいますから、草履番は玄関に到着した家臣に草履を差し出す仕事に忙殺されます。
なにより、新人ですから先輩家臣の顔と名前がなかなか一致しない上に、何十足もある草履の中からお目当ての草履を探し出すのにも時間がかかり、「遅い!」「その草履はワシのではない!」「草履番もまともにできんのか!」と先輩家臣達に叱責の雨アラレを受けてしまいます。
しかし万千代「日の本一の草履番になってやる!」と一念発起。
まず、草履棚を作り、置き場所に先輩家臣の名前を紙に書いて貼りました。これにより、先輩家臣の顔と名前と草履を間違えなくなりました。
さらには、棚から取った草履を手裏剣の様に投げて先輩家臣の足元にピタっと揃え置くという、文字通りの離れ業を修練によって身に付けることによって、時短と先輩家臣の感嘆を得て、万千代の草履番は高評価を得ます。
ここまでの話は、第40回「天正の草履番」|あらすじ|NHK大河ドラマ『おんな城主 直虎』にて動画でご確認を頂けます。私の拙い文章では伝わらないときはご参照ください。
しかし、高評価が過ぎて草履番を引き継ぐ者がおりません。
この者に草履番を引き継いだなら小姓にしてやると言われて紹介されたのが、ノブと自称する愚鈍そうな中年のおじさん。
ノブはその外見とは裏腹に三日で先輩家臣の顔と名前を覚えるのですが、若い万千代のようにキビキビとは動けず、ましてや手裏剣技などできません。
ところがある日、まだ先輩家臣が玄関先に来ていないのに、ノブは草履を揃え置くのです。
驚く万千代をよそに「まぁ見ていてごらんなさい」と余裕のノブ。
間もなく先輩家臣が玄関先に到着するのですが、あらかじめ揃え置いた草履とその持ち主がピタリと一致。先輩家臣達は玄関に来る前から用意されている草履を不思議に思う様子を見せつつ、草履を履いて門を出ます。
さて、お次は…と、やはりあらかじめ草履を3足用意するノブ。
ところが今度は先輩家臣が2名しか来ません。万千代が「それ見たことか」と思っているところ、ノブが先輩家臣の1人に「本日は大久保様とご一緒ではないのですか?」と尋ねます。
つまるところ、ノブは草履番を務める中で、先輩家臣が下城する際のパターンや傾向をよく観察し、誰が誰とどの順番に玄関を出るのかを高確率で予測することができるようになったことで、あらかじめ草履を揃え置くことを可能としたのですね。
こちらはNHKの5分間ダイジェスト動画にはありませんので、なんとか私の文章で理解してくださるよう願います。A^^;
さて、ここから剣道ネタ。
剣道でよく使われる「先」について、先に挙げた草履番の話を元に解説してみましょう。
草履番という仕事において万千代は、先輩家臣が玄関に出てくるという事象に対し、草履棚や手裏剣技などの万全な事前準備によって、後れを取ることなく対処し、充分にその務めを果たしました。
これを「先」と言います。
剣道に当てはめますと、相手の打突や防御に後れを取ることなく打突することになります。草履棚は剣道の正しい構えに、手裏剣技は打突の速さと正しさに相当するでしょう。
これが「先」です。
これに対してノブは、先輩家臣が玄関に出てくるという事象のパターンと傾向を掴むことによって正確に予測し、その予測を元にあらかじめ草履を揃え置くことで、万千代以上の対処を実現しました。
これを「先の先」と言います。
剣道に当てはめますと、相手の打突意思または防御意思を読み取ることによって相手の打突や防御動作を正確に予測し、その予測を元に打突することになります。観察することによってパターンと傾向を掴む点は草履番と全く同じです。
これが「先の先」です。
さらには、この草履番エピソードでは出てきませんでしたが、例えば「先輩を差し置いて後輩が先に下城するというのはいかがなものでありましょうなぁ」などという話を家臣の中に蔓延させることによって、下城順序の固定化を促してしまうという策を講じたならば、これは「先先の先」と言えます。
剣道に当てはめますと、間合やこちらの気勢、繰り出す打突の組合せなどによって、こちらが望む打突をこちらが望むタイミングで相手が打たざる得ない状況に追い込み、相手がまんまと打ってきたところを応じ技で一本を取るという形になります。
これが「先先の先」です。
うーん、解説になっているか自信が無いです。
やっぱり剣道教室でこのネタを使うのはやめておこうw
まー、それはともかくとしまして、身体能力を鍛え、打突の大強速軽を向上させ、ひたすらに純粋に「先」を取り合う剣道も面白いのですが、「先の先」や「先先の先」を効かせることによって、老練な剣士が若武者を打ち込む場面さえも表れるのが、剣道の奥深さかと思います。
とくに、身体能力の低下が抵抗もむなしく著しい私らアラフィフ剣士は、「先の先」あるいは「先先の先」を意識しつつ、その礎となる「先」を磨かねばなりませんね。
オチはやはり自省になりました。はい、ガンバリマス。A^^;