八千代大会中止経緯
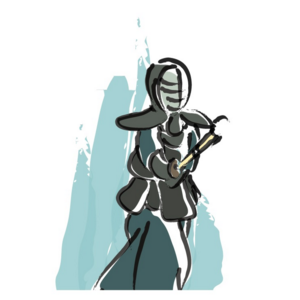
すでに八千代剣道教室ウェブサイトには掲載済みですが、本年3月15日(日)の開催を予定していた第41回八千代町近隣剣道大会=八千代大会は、中止することにいたしました。
拙ブログでは、その経緯について書いておこうと思います。
まず、前提として八千代大会について。
競技種目は剣道。個人戦7部門(小4/5/6/中学男子/同女子/一般男子/同女子)と学年指定混在型(先鋒から順に小4/5/6/中学生/中学生)の団体戦1部門を設けてます。
参加選手数の総計は約450名。これに審判員約50名、大会係員約30名、選手とほぼ同数の観客を含めて約1,000名が八千代町総合体育館に集まります。
試合場は4つ。剣道大会の会場規模としては小さく、そこに会場キャパの限界に近い人数が集まるという点が特徴的かと思います。
参加団体は約30。主に茨城県南西部の剣道団体からご参加を頂いておりますが、県外からも2~3の剣道団体からご参加を頂いております。
年齢層ですが、選手は小学生6割、中学生3割、一般1割。なお、一般は30歳以上の年齢制限を設けており、平均年齢は40歳くらいです。
観客は小中学生の引率を兼ねたご家族による観客が大部分で、30~40代が中心。幼いお子様連れや、孫の応援に来られたお年寄りの姿も目立ちます。
審判員は40~50代が中心ですが、60代の先生方もおられます。来賓は高齢者の方もおられます。
というわけで、大会に集まる皆様の年齢層は、未就学児から後期高齢者まで、幅広いものがあります。
開会式が午前9時、閉会式は午後4時近くになります。
当然にしてお昼を跨ぎますので、審判員及び係員には昼食(弁当)の提供があり、選手および観客は持ち込んだお弁当を定められたエリアで飲食します。
長くなりましたが、ここまでが前提です。
八千代大会参加申込書の〆切を2/14(金)に設定してありましたので、2/16(日)の時点でドローソフトへの選手登録をほぼ終え、あとは2/21(金)に予定していた大会運営委員による大会準備会にて改めての選手登録の確認と組合せ抽選を実施するばかりという状況でした。
ところが週明けの2/17(月)、宮内庁より2/23(日)の天皇誕生日一般参賀および記帳を中止する旨の発表と、東京マラソン財団より3/1(日)に開催される東京マラソンの一般参加者出場を取りやめとする発表があり、これを機に自粛ムードが高まり始めます。
しかし、この時点では、私はまだ他人事に捉えてました。
契機はその翌日である2/18(火)。火曜日は定例の稽古日ですので、稽古を終えての帰宅後にPCから剣道教室ブログに稽古記録を書き込み、そのついでにTwitter投稿をする中で、厚労省公式のツイートが目に入りました。
また、人が密着するような大規模イベントの開催等について、開催時期の見直しの必要性などを含め、専門家の意見を聞き、皆様にお知らせします。
— 厚生労働省 (@MHLWitter) February 18, 2020
これをイベント開催/中止についての指針が近日中に発表されるものと捉え、情報収集のアンテナを高くすることにしました。
対応が早かったのは大阪府でした。
厚労省発表の翌日2/19(水)の大阪府知事のツイート。
また、同趣旨の当面1ヶ月間のイベント、集会の中止又は延期措置のお願いを大阪市を含む府内43全市町村、経済団体等に府から呼びかけをしています。最終は各市町村長、各主催者の判断になります。感染拡大初期の現在、新型肺炎の「急激な感染ピーク」を抑え込むことが重要です。ご理解をお願いします。
— 吉村洋文(大阪府知事) (@hiroyoshimura) February 19, 2020
そして2/20早朝のニュースにて
新型ウイルス感染拡大防止 具体的な対処方針策定へ 政府 #nhk_news https://t.co/zwR4E9XLnE
— NHKニュース (@nhk_news) February 19, 2020
大規模イベント 開催の判断の目安 公表へ
一方、各地でイベントの自粛や中止の動きが広がっていることから、加藤大臣は、大規模なイベントを開催する際の判断の目安や注意点などの考え方を20日にも、公表することにしています。
と、ありましたので、おそらくは同様の指針が厚労相から示されるのだろうと予想し、注目をしていたのですが、夕方になっても厚労相声明はありませんでした。/
2/20(木)は19時より、八千代町体育協会の定例理事会がありましたので、厚労相声明を得てから理事会に臨みたかったのですが、それを得ぬまま理事会に出席。
町体協理事会では今年度の決算見込み、来年度予算、来年度総会日時、「体育協会」から「スポーツ協会」への名称変更などの予定されていた議案が滞りなく議決されてそのまま終わりそうになったので、慌てて挙手して「町体協としての新型コロナウイルスに対するイベント開催/中止の指針を示してもらえないだろうか?」と問いかけました。
しかしそれに対する答えは「各イベントを主管する競技連盟にて検討して頂き、その検討結果に町体協として協力する」というものでした。
主催(町体協)と主管(競技連盟)ってそういう関係だっけ?
本来は逆じゃないのかな?
とモヤモヤした気持ちを抱えたまま、下駄を預けられる形になってしまったのでした。
町体協理事会と時を同じくして厚労相声明が発表されたらしく、その内容が↓これ↓
【#新型コロナウイルス 「大規模なイベントの開催について」】
大規模イベントの開催について、加藤勝信厚生労働大臣からお願いがあります。 pic.twitter.com/EHV4kZI28L— 厚生労働省 (@MHLWitter) February 20, 2020
イベント等の主催者においては、感染拡大の防止という観点から、感染の広がり、会場の状況等を踏まえ、開催の必要性を改めて検討していただくようお願いします。なお、イベント等の開催については、現時点で政府として一律の自粛要請を行うものではありません。
なお、新型コロナウイルス感染症の今後の感染の広がりや重症度を見ながら適宜見直すこととしています。
町体協の答と全く同じ内容に苦笑するほかありませんでした。
せめて茨城県はなにか指針を示してくれないものだろうか?
と、藁をもすがる気持ちで茨城県のウェブサイトを確認しましたところ…
朝日:新型コロナウイルスに関してですが,県内の市町村でもイベント中止などが相次いでいるようですが,県として,イベント実行に関することなどで,何か指針などを出すような予定はございますか。
知事:イベントについて,特に指針を出す予定は特段ございません。
ただ,ここ1カ月ちょっとというのが感染のピークの山場になるというお話ですので,そういう時期においては,不必要ということはないのですが,あまりたくさんの方々が集まるようなイベントがもし変更できるのであれば,変更した方がいいのではないかという認識は持っています。それに伴って,茨城空港の10周年記念のイベントも我々は延期させていただきました。
暗澹たる気持ちになりました。orz
仕方がないので独自に検討を重ねたわけですが、
- 剣道の競技特性上、選手および審判員間の飛沫感染リスクが他の競技と比較して高いこと
- 屋内イベントであること
- 参加者間の距離が十分に取れない会場環境であること
- 食事提供および弁当持ち込みがあること
- 審判員および来賓に高齢者が含まれること
以上のように、大会を開催するために回避すべきリスクが多岐に渡り、それに対して有効なリスク低減策を見出すことができません。
- 茨城県内での感染事例がまだ報告されていないこと。
この1点のみが大会開催への光明と言えましたが、茨城県南西部より東京に通勤している方が珍しくない状況では、茨城県内で感染事例が報告されるのも時間の問題です。
その1例目が八千代大会での感染となったときの打撃を考えると、大きなリスクとなり得る点とも言えるのです。
これら状況を整理し、すでに中止発表のあった他の都県の剣道大会情報と、近隣市町のイベント中止情報を提示して、2/21(金)の大会運営委員による大会準備会にて協議した結果、全会一致で大会中止が議決されたのでした。
この席上では努めて明るく振る舞いましたが、大会2日前に東日本大震災で被災して大会中止に追い込まれた記憶が揺り戻され、とても悔しいし悲しいというのが本音です。
子ども達も、とくに今年は小6の急成長があり、その力を地元で発揮するべく意気込んでましたので、その地元大会が無くなったことによる喪失感は否めないものがあります。
また、八千代大会を今年度最後の大会としている剣道団体も多く、大会中止を惜しむ声は日に日に高まってます。
しかしながら、地域社会の後押しが無ければ成立しない剣道なのですから、地域社会にとって善となる判断をせねばなりません。
となると、選択肢は1つしかありませんでした。
3月後半には剣道のビッグイベントが目白押し。
水戸大会、魁星旗(秋田)、高校選抜(愛知)、スポ少全国大会(長野)などなど。
これら大会の主催者は対応に苦慮されていることと思います。
八千代大会のようなローカル大会でさえ、これだけ逡巡したのですから。
そのような状況下で、厚労省および政府、大阪府など一部を除く都道府県は元より、全剣連、全道連、日本スポーツ協会、全国高体連、日本中体連といったあたりがイベント開催/中止判断の指針を示さず現場任せにしていることは、責任論、あるいは公衆衛生や国内経済の観点から、おかしいと思います。
今件は完全に政治・行政マターの事案であり、大阪府のように目的を明確にして日時を区切るか、開催するために必要な措置を明確に示すか、いずれにせよ全国統一基準で臨まないと、終わりなき自粛ムードに流されてしまい、新型コロナウイルスによる死者よりも、経済が回らないことによる死者の方が多くなりかねません。
大会開催/中止の判断を迫られた1人として言いますが、今のこの混乱は失政によるものです。
この混乱の最中にそれを責めるつもりはなく、それぞれがそれぞれのポジションで頑張るほかありませんが、国や都道府県の政治行政に携わる方々には今からでも新型コロナウイルスへの取り組みを改めて頂きたいと切に願ってます。