師弟同行
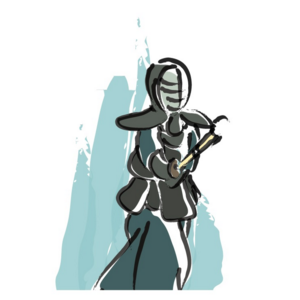
ダルビッシュ投手のコメントには考えさせられました。
僕が監督なら、週2回は休む ダルビッシュの高校野球論(朝日新聞デジタル)より一部抜粋
日本の高校野球では、正しい知識を持たない監督やコーチが、自分の成功体験だけに基づいて無理を強いる。そういう側面があると感じます。改善されてきているのでしょうが、壊れてしまう選手、苦しむ選手は後を絶ちません。
指導者には正しい知識を身につけて欲しい。例えば休養の重要性です。筋力トレーニングは、ほぼ毎日頑張るよりも、週に3日程度は休みながら行う方が結果は上になったりするのです。いまだに冬に10日、夏に5日程度しか休まないような野球部が珍しくないでしょう。僕が監督なら週2回は休むし、全体練習も3時間で十分。そのくらいの方が成長するのです。
だから、日本の高校生は「頑張らない!」で、ちょうどいい。もちろん、頑張るところと頑張らないところを自分で見分けられるように知識を得る努力は必要ですが。指導者にはもっと頑張って欲しい。球児を取り巻く環境を変えるには、指導者が変わらないと。
一応の補足を入れておきますと、なにをもって正しいとするのかは目的や目標によって異なります。
高校在学中の早い段階、あるいは甲子園出場を狙える高校を選択した時点で、プロ野球や米メジャーリーグで活躍することを視野に入れていたダルビッシュ投手の視点で、正しいとする価値観。
指導する野球部員の大多数は野球以外の仕事で生計を立てることになるという現実を前提に、あくまでも教育の一環としての野球指導が求められている高校野球指導者の視点で、正しいとする価値観。
この両者の相違は大きいものがあります。
そして、指導者側が立場的優位によって選手側の価値観を抑え込みがちであるため、選手側の視点から語られることは、指導者側への批判という形になってしまいがちです。元ジャイアンツの桑田投手などはその典型でしょう。
功成り名を成した人物の意見は強烈なインパクトがありますけれど、冒頭で申しましたように、目的や目標によって正しいとすることは異なりますので、万人に正しい意見とは限らないのです。
よって、先に取り上げた記事は、指導者側の視点で語ることのできる人物にもインタビューすることで完成するのではないかと思ってます。
それを朝日新聞がやってくれるとは限らないので、指導者側の視点で高校野球の諸問題を語られている記事を探して読むことにより、多角的な視点による、より正しい現状認識が得られるのでしょうね。
前置きが長くなってしまいましたが、ダルビッシュ投手の言う「正しい知識を持たない監督やコーチが、自分の成功体験だけに基づいて無理を強いる」というのは耳の痛い話でした。
なぜ門外漢の私なのに耳が痛いのかと言いますと、選手の様々な能力や成績があれだけ数値化されている野球界でそうならば、それらが全くと言ってよいほど数値化されておらず、指導法に関する書籍も情報も野球界とは比べ物にならないほど少ない剣道界はどうなのよ?と疑問に思ったからです。
つまり「自分の成功体験だけに基づいて無理を強いる」の蔓延りは野球界よりも剣道界の方が深刻だよなぁということです。
私も指導者の端くれですので、剣道に関する知識や情報は常に最新のものを取り入れ、指導に誤りを見つけたら早期に正す姿勢が必要だ、と、良き示唆を得られたことに感謝した次第です。
ただ、剣道の場合は「師弟同行」という良い言葉があります。
師も弟子も同じ修行者であり、師と弟子は同じように修行すべし。
読んで字の如しではありますが、私のように小学生相手でも、実践してみると実に奥の深い言葉です。
師弟が同行する限り、その視点は限りなく近いものになります。
ともすれば「自分の成功体験だけに基づいて無理を強いる」を招きやすくもなりますが、指導者自身も実践することでその誤りに気付きやすくもなるでしょう。
ただ、野球だとそれは難しい。
例えば高校時代のダルビッシュ投手のボールを打てる指導者などいないでしょう。
剣道の場合、それが出来てしまう。
や、出来ないと指導者としてマズイのです。
体力的なこと、運動能力が問われることはともかくとして、指導しようとしていることが実践できないということは、指導しようとしている剣の理に誤りがあるということであり、それでは弟子が付いてきてくれませんからね。
そんなわけで、私の技量で指導できるのは中学生までです。
高校生は私が出来ることなど全て出来ますし、それ以上のことが求められますので。
よって、今もたまに稽古する次男とは師弟関係が解消されているのですが、にも関わらず、彼は私を師として立ててくれます。これも剣道の良きところ。
この師弟同行をしない指導者も学校剣道部等でわりと見かけますけれども、よほど勉強をして剣の理を確立していないと正しい指導は難しいだろうに、ホントに大丈夫なのかなぁと心配になります。
それぞれに理由や事情はあるのでしょうが、せめて稽古着くらいは着てほしいものですね。